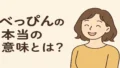こんにちは、じんさんです。
「敷居が高い」という言葉、よく耳にしますよね。
「高級そうで入りにくい」とか「格式があって気後れする」といった意味で使う方も多いんやないでしょうか。
でもね、それって本来の意味とは少し違うんです。
今日は、じんさん自身が“とある喫茶店”で感じた出来事を通して、
この言葉に込められた本当の意味と、時代とともに変化した使われ方を一緒に見ていきましょうか。
「敷居が高い」とは?語源と本来の意味
「敷居が高い」という言葉の語源は、家の出入り口にある“敷居”という部材にあります。
ここをまたいで中へ入る=相手のもとを訪ねる、という意味合いがあるんです。
昔は、「過去に迷惑をかけた」「顔向けできない」という理由で、
その人の家の敷居をまたげない、つまり行きたくても行けない心理的ハードルを「敷居が高い」と表現していました。
本来の意味は、
「気まずくて行きづらい」「申し訳なさがあって訪れにくい」
であり、高級・上品・格式があるから入りにくい、という意味ではないんですね。
「高級で入りにくい」は誤用?現代の使われ方
とはいえ、現代では「高級な店=敷居が高い」と表現されることも一般的になってきています。
たとえば──
- 静かで落ち着いた老舗の料亭
- ドレスコードが必要なレストラン
- 初対面では入りにくい高級バー
こうした場所に「気後れ」することを、「敷居が高い」と言う人が増えています。
これは「ハードルが高い」「気軽に行けない」というニュアンスと混ざり合って広まった使い方ですが、厳密に言うと、本来の意味とは異なります。誤用とまでは言わずとも、使い分けには注意が必要です。
敷居が高くて入れなかった理由:じんさんの体験
あれは、たしか10年ほど前のことですわ。
仕事でちょっと嫌なことがあって、気持ちがざわついたまま、近所の喫茶店「ひぐらし」に飛び込んだときのこと。
いつものようにカウンターに座って、コーヒーをひと口。
でも、心が乱れていたんでしょうな。
「……今日の、ちょっと苦くないか?」
そんなふうに、つい言ってしもうたんです。
マスターは無言で軽くうなずいた。
本当なら、それだけで終わった話なんですが――
わしはなぜか、それが気に食わんかった。
ちょっと語気を強めて、「こっちは毎週来てるんやで。もうちょい愛想があってもええんとちゃうか?」
……今思えば、完全な八つ当たりです。
マスターに非はない。
わしの気持ちが乱れていただけなんです。
するとマスターは一拍置いて、落ち着いた声で言いました。
「うちのコーヒーは、毎回同じ豆を同じように淹れています。
でも、人の舌は日によって違うもんです」
……正論でした。胸に突き刺さりましたわ。
でも、素直になれなくてね。
「……もうええわ。ありがとな」
そう言って、背を向けて出てしもうたんです。
それ以来、「ひぐらし」には行けませんでした。
行けないんやなく、自分で行かなくしてしまったんです。
「申し訳なかったなぁ」「謝りたいなぁ」
そんな気持ちはずっとあったけど、それ以上に、気まずさと後悔が勝ってしまった。
扉の前で何度も足が止まりましたが、どうしても敷居をまたげなかった。
わしにとって「敷居が高い」という言葉は、まさにこの出来事と重なります。
なぜ敷居が高いの意味が変化してしまったのか?
言葉というのは、生き物です。
時代や人々の感覚によって、意味や使い方が変化していきます。
「敷居が高い」もまた、本来の意味があまり知られなくなり、
「なんとなく入りづらい」「高級そうで気後れする」といった感覚と結びついてしまった結果、
現在のような使い方が広まったと考えられています。
SNSやテレビ番組などでも誤った文脈で使われることが増えたため、
誤用が定着したように見えるのです。
「敷居が高い」の自然な使い方・例文
正しい使い方の例:
- 「以前、失礼なことを言ってしまったから、あの店には敷居が高い」
- 「ご無沙汰しているけど、迷惑をかけた手前、実家の敷居が高い」
注意が必要な例:
- 「あのレストランは高級すぎて敷居が高い」
- 「格式があって入りにくい店=敷居が高い」
上のような表現も一般化していますが、本来の意味からはずれていることを覚えておくとよいでしょう。
敷居を高くしているのは、自分の心かもしれない
「敷居が高い」という言葉には、過去の自分に対する後悔や、相手への申し訳なさといった、
人と人との関係性がにじんでいます。
高級とか格式とかじゃない。
本当に行きづらいのは、「自分の心が作った壁」なんです。
じんさんにとって「ひぐらし」は、そういう意味で敷居が高くなってしまった場所でした。
でもね、あれから時が経った今、いつかまたあの扉を開けてみようかと思うこともあるんです。
じんさんのひとこと
言葉には、人の気持ちが染みこんでますな。
「敷居が高い」と感じたとき、それは相手が冷たいわけやないかもしれません。
自分の気持ちが、そうさせてるんやと思うんです。
だからこそ、ちょっと勇気を出して、“その敷居”をまたいでみると、
思いがけない優しさや、懐かしい笑顔に出会えることもあるんですよ。
じんさんについて
じんさん――70代後半。
言葉や風習の奥にある「日本人のこころ」を大切に思い、日々の暮らしの中で見つけた気づきや学びをやさしく語ります。
かつての人づき合いや、言葉に込められた意味を振り返りながら、
現代の私たちにも通じる“和のたしなみ”を伝えていくのがじんさんの役目です。